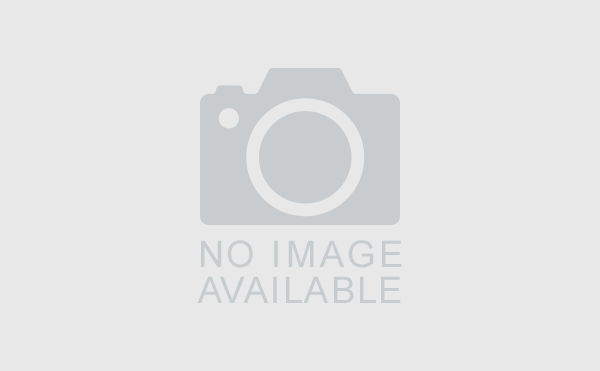第58回 中国での新型コロナウイルス感染症蔓延期における労働紛争のモデル事案についての分析
概要
中国の最高人民法院及び人的資源社会保障部は「労働人事紛争のモデル事案の第一弾を合同で公布することについての通知」(以下、「本通知」)を公布した。本稿では、本通知の中の新型コロナウイルス感染症蔓延に関わる主要なモデル事案について紹介する。
はじめに
中国における新型コロナウイルス感染症の蔓延は、本稿執筆時点では、これまでのところ他国と比べてコントロールされている状況にあるといえる。しかし、それでも、感染症蔓延に伴う労働紛争事案は、中国においても相当数生じている。このような状況を受け、最高人民法院及び人的資源社会保障部は「労働人事紛争のモデル事案の第一弾を合同で公布することについての通知」1(以下、「本通知」)を合同で公布した。本通知は、モデル事案を通じて、労働紛争事案の処理について指導を行う内容となっており、「事案の基本的な経緯」「申立人の請求の趣旨」「処理結果」「事案の分析」及び「モデルの意義」で構成されている。また、事案の中には新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う労働紛争事案も含まれている。
在中日系企業において、既にこのような労働紛争事案を抱えているところもゼロではない。また今後、発生するリスクもないとはいえない。そこで参考までに、中国における労働紛争の処理について、本通知の中にある新型コロナウイルス感染症蔓延に関わる主要なモデル事案を要約して紹介する。
労働紛争のモデル事案
<事案1>
使用者(経営者)は新型コロナウイルス感染症の蔓延が不可抗力に該当することを理由に、労働契約を途中で終了させることができるのか。
(1)事案の基本的な経緯
申立人:A氏(物流会社の従業員。他省に向けた商品運送業務に従事、月額賃金:5,000元)
被申立人:A氏が勤務するB社(物流会社)
新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受け、B社は所在地区の人民政府が施行する感染防止措置に従い、2020年2月3日より業務を停止した。2月末、B社は、感染症蔓延が不可抗力に該当することを理由として、A氏との労働契約を途中で終了させた。2月の業務停止期間中、A氏に出勤の必要がなかったため、B社はA氏に賃金を支払わなかった。そのため、A氏は3月に労働人事紛争仲裁委員会(以下、「仲裁委員会」)に仲裁を申立て、B社が2020年2月の賃金5,000元を支払う判断を下すことを要求した。
(2)判断・判決の結果
仲裁委員会はB社に対して、A氏へ2020年2月の賃金5,000元を支払うよう判断を下した。B社は仲裁判断を不服として提訴したが、一審裁判の判決は仲裁判断と同様であり、B社は控訴せず、一審判決が発効した。
(3)事案の分析
本事案の争点は、B社が不可抗力を理由としてA氏への賃金支払いを拒否することができるのかという点にある。人的資源社会保障部、最高人民法院等の7つの部門による「感染症蔓延に関わる労働関係に関する問題の適切な処理についての意見」(人社部発〔2020〕17号)(以下、「意見」)第1条には「感染症蔓延の影響を受け、元の労働契約を確かに履行することができない場合、労働契約の履行を一時停止するというやり方を講じてはならないが、企業と労働者が協議により合意した上、法により労働契約を変更することができる」と規定されている。そのため、労働契約の主体は新型コロナウイルス感染症の蔓延が不可抗力であることを理由として、一方的に労働契約の履行を途中で終了させてはならない。
(4)弊所コメント
上記事案を踏まえると、類似案件の適切な処理方法としては、以下の方法が考えられる。
1)協議により労働契約を変更する。
または
2)一賃金支払周期内においては通常の賃金を支払い、一賃金支払周期を越える場合は、各地の規定に基づき、現地の最低賃金基準を下回らない賃金を支払う。
上記、2)については、人的資源社会保障部弁公庁が公布した「新型コロナウイルス感染症の蔓延防止・コントロール期間における労働関係問題を適切に処理することについての通知」2(以下、「5号文書」)第2条に、「企業の業務・生産の停止期間が一賃金支払周期内であった場合、企業は労働契約に規定される基準に従って従業員に賃金を支払わなければならない。一賃金支払周期を越えた場合において、従業員が通常の労働を提供したときは、企業が従業員に支払う賃金は現地の最低賃金基準を下回ってはならない」と規定されており、これが根拠となる。
<事案2>
疫病発生の影響を受け、使用者が一部の業務・生産を停止した場合、業務・生産の停止の規定に従って賃金を支払うことができるのか。
(1)事案の基本的な経緯
申立人:C氏(自動車会社D社のカスタマークラブの従業員、月額賃金:8,000元)
被申立人:D社(自動車会社:自動車部品の生産、自動車組立及び車両販売等)
D社は、毎月10日に、前月4日~当月3日までの賃金を支給していた。2020年2月3日以降、D社は部品生産、自動車組立、車両販売部門の業務を立て続けに再開した。だが、新型コロナウイルス感染症蔓延の防止・コントロールにより、カスタマークラブは業務を再開することができず、C氏が所属する同クラブの10人余りの労働者は、いずれも業務停止状態となった。3月10日、D社はC氏に2月分の賃金を支払い、4月10日には、生活費基準に従ってC氏に3月分の賃金を支払った。しかし、D社が業務停止を理由に悪意をもってその賃金を引き下げたと主張するC氏は、仲裁委員会に仲裁を申立てた。そして、D社が3月4日~4月3日までの3月分賃金の差額6,460元を支払うよう、仲裁によって判断を下すことを要求した。
(2)判断の結果
仲裁委員会は、C氏による仲裁申立ての趣旨を棄却する判断を下した。
(3)事案の分析
本事案の争点は、新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受けたD社の一部業務・生産停止について、業務・生産停止の規定に従ってC氏に賃金を支払うことが可能か否かという点にある。5号文書には、「企業の業務・生産の停止期間が一賃金支払周期内であった場合、企業は労働契約に規定される基準に従って従業員に賃金を支払わなければならない。一賃金支払周期を越えた場合において、従業員が通常の労働を提供したときは、企業が従業員に支払う賃金は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。従業員が通常の労働を提供していない場合、企業は生活費を支給しなければならず、生活費の基準は各省、自治区、直轄市が規定する弁法に従う」と規定されている。
「賃金支払暫定規定」第12条には、「労働者の原因によらない組織の業務、生産の停止期間が一賃金支払周期内であった場合、使用者は労働契約に規定された基準により労働者に賃金を支払わなければならない。一賃金支払周期を越えた場合において、労働者が通常の労働を提供したときは、労働者に支払う労働報酬は現地の最低賃金基準を下回ってはならず、労働者が通常の労働を提供していないときは、国の関連規定により処理しなければならない」とも規定されている。上記の規定は、使用者の業務・生産停止期間中に労働者が通常の労働を提供できるケースと通常の労働を提供することができないケースについてそれぞれ明確にしているだけで、適用条件について使用者の全部の業務・生産停止に限定しているわけではないことが分かる。
調査によると、D社の一部の業務の停止は、C氏1人を対象として決定されたものではなく、カスタマークラブの10人余りの労働者に対し、差別なく適用されたものである。そのため、仲裁委員会は、D社による一部の業務停止の決定に主観的な悪意が存在するというC氏の主張を採用せず、同社がC氏の所属する部門の業務停止を決定し、かつ5号文書の規定を適用してC氏に賃金を支払ったことは、不当なものではないとし、C氏の仲裁の申立ての趣旨を法により棄却した。
(4)弊所コメント
上記のとおり、結論としては、使用者が全部の業務・生産停止を行う必要があると規定されているわけではないので、一部(ある部門のみ)の業務・生産の停止についても業務・生産の停止の規定に従って賃金を支払うことが可能である。ただし、上記でも言及されているとおり、ある部門の業務・生産停止は、当該部門の従業員に差別なく適用すべきであり、特定の従業員に対してのみ業務停止命令を出すなどの取扱いをしないように注意すべきである。
<事案3>
感染症蔓延の影響を受け、業務・生産の再開が延期された場合、使用者は一方的に労働者に年次有給休暇を使用させるよう決定する権利を有するか。
(1)事案の基本的な経緯
申立人:E氏(F社に料理人として勤務、月額賃金:8,000元)
被申立人:F社(E氏が勤務する飲食会社)
E氏は、2019年より毎年5日の年次有給休暇を取得できるようになったため、年を跨いで休暇を取得することを書面で要求し、勤務するF社の同意を得ていた。2020年2月3日、現地の市政府は全市の感染症蔓延防止・コントロールにより、全ての企業に対し業務・生産の再開を2月17日まで延期するよう要求した。F社はE氏に対し業務再開の延期を通知し、かつ2月3日~14日の期間中に2019、2020年度の年次有給休暇を全て使用するよう通知した。E氏は同意しない旨を示したが、F社はE氏に当該通知に従うよう要求し、かつE氏に2月3日~14日までの期間の賃金を支払った。3月9日、F社の業務再開後、E氏が何度も無断欠勤したため、飲食会社はE氏との労働契約を解除した。E氏は仲裁委員会に仲裁を申立て、F社が2019、2020年度の未使用である年次有給休暇分の賃金6,620.69元(8,000元/21.75日×6日×300%)を支払う判断を下すことを要求した。
(2)判断の結果
仲裁委員会はE氏の仲裁の申立ての趣旨を棄却する判断を下した。
(3)事案の分析
本事案の争点は、F社がE氏の同意を得ずに業務・生産の再開延期期間中にE氏に年次有給休暇を使用するよう通知したことが、適法であったかという点にある。「従業員年次有給休暇条例」第5条第1項には、「組織は生産、業務の具体的な状況に基づき、また従業員本人の意思を考慮して、従業員の年次有給休暇を統一的に手配する」と規定されている。「企業従業員年次有給休暇実施弁法」第9条には、「使用者は生産、業務の具体的な状況に基づき、従業員本人の意思を考慮して、年次有給休暇を統一的に手配する」と規定されている。「新型コロナウイルス感染症蔓延の防止・コントロール期間中にきちんと労働関係を安定させ、企業の業務・生産再開をサポートすることについての意見」には、リモートワークの条件を有さない企業については、年次有給休暇、企業が自ら設ける福利休暇等の各種休暇を優先的に使用するよう従業員と協議する」とも規定されている。
これらの条項により、使用者は労働者の年次有給休暇を統一的に手配する権利を有し、労働者との協議は使用者が履行しなければならない手続ではあるが、「協議により合意しなければならない」ことが要求されているわけではないことが分かる。労働者が同意するかしないかに関わらず、企業は協議という手続を踏んだ後、統一的に年次有給休暇を手配することができる。
(4)弊所コメント
上記のとおり、企業は、労働者に業務・生産の再開延期期間中に年次有給休暇を優先的に使用させるよう手配することが可能である。ただし、その場合には、労働者の実際の状況をできる限り考慮し、法による協議という手続を踏み、かつ法により年次有給休暇中の賃金を支払わなければならない点に注意が必要である。
**********************************************************************
1 人社部函[2020]62号、2020年7月10日公布、同日施行
2 人社庁明電[2020]5号、2020年1月24日公布、同日施行
(2021年1月27日作成)
*本記事は、一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。
*本稿は、三菱UFJ銀行会員制情報サイト「MUFG BizBuddy」(2021年1月掲載)からの転載です。