第2回 パロディ商標の適法性
「パロディ商標」は、風刺、からかいの手法によって既存の商標を模倣して作り出された商標であり、通常、模倣対象は比較的有名な商標である。そうでなければパロディの効果は得られない。例えば、台湾では「エルメス(HERMES)」(図1参照)及び「シャネル(CHANEL)」(図2参照)を模倣したパロディ商品が登場したことがあり、また日本では、「SHI-SA」(図3参照)による「PUMA」模倣、「フランク三浦」(図4参照)による「FRANCK MULLER」模倣等の事件がある。

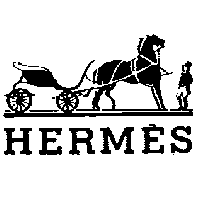
図1
左は登録しようとしたパロディ商標「バナナバッグ(BANANE)」、右は「エルメス(HERMES)」商標
(写真・図の出所:台湾の知的財産裁判所2011年度行商訴字第104号判決原文)


図2
左はパロディ商品の「塗料の落ちた留め金具」、右は「シャネル(CHANEL)」商標
(写真・図の出所:台湾の知的財産裁判所刑事判決2014年度刑智上易字第63号原文)


図3
左は登録しようとしたパロディ商標「SHI-SA」、右は「PUMA」商標
(写真・図の出所:日本の知的財産高等裁判所平成21年(行ケ)第10404号商標登録取消決定取消請求事件の原文)
![]()
![]()
図4
左は登録に成功したパロディ商標「フランク三浦」、右は「FRANCK MULLER」商標
(写真・図の出所:日本の知的財産高等裁判所平成27年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件の原文)
米国では、法律の実務上「パロディ商標」についての理論が発展してから久しく、例えば2007年のLouis Vuitton Malletier対Haute Diggity Dog,LLCという事件(連邦下級審判例集第3シリーズ第507巻252頁、第四巡回区裁判所、2007) (以下「LV事件」という)の判決では、「パロディ」について「パロディは、それがオリジナルでもあり、また、オリジナルではなくパロディで代えたものに過ぎない、という二つの相対するメッセージを同時に伝えなければならない。そして後者が重要であり、そこではパロディとオリジナルを区別するだけでなく、明瞭なあてこすり、揶揄、からかい又は娯楽等の要素を伝える必要もある」という解釈がなされており、「パロディ商標」は、当該解釈に合致していれば、模倣対象の商標との混同を生じることはないと判断される可能性がある。
米国における上記の判決は、台湾の知的財産裁判所の二つの判決で引用されたことがあり、その一つは、前記の「エルメス(HERMES)」を模倣した「バナナバッグ」事件である。裁判所の判断は「米国の第四巡回区控訴裁判所のLouis Vuitton Malletier 対 Haute Diggity Dog, LLC.事件における見解を参照すれば分かるように、本件の商標は公正利用されたパロディ品に該当し、また、拒絶査定の根拠となった商標と混同・誤認が生じる可能性などは生じない。しかしながら、調べによれば、原告が提示した米国の第四巡回区控訴裁判所のLouis Vuitton Malletier 対 Haute Diggity Dog, LLC.事件における基本的事実は本件とは異なっており、当事者も異なり、また我が国の商標登録制度では先願登録主義を採用しているが、米国では先使用主義を採用しており、両国の商標に係る法律制度は異なっているため、上記の米国の裁判例は確かに、原告に有利な事実認定の証拠として本件で引用することはできない」というものであった(知的財産裁判所行政判決2011年度行商訴字第104号参照)。
もう一つは、前記の「シャネル(CHANEL)」を模倣した「塗料の落ちた留め金具」事件である。
裁判所の判断は、「学理上のいわゆる『商標のパロディ品』(parody)は、言論の自由、表現の自由及び芸術の自由の尊重に基づき、商標権に対し合理的な制限を加えるものであるが、商標法はそもそも、商標権及び消費者の利益を保護し、市場の公平な競争を維持し、商工業を営む企業の正常な発展を促進するために制定されたものであり、商標権者は商標の使用及び商標権に対する保護を通じて徐々にそのブランドの価値を確立し、また関連消費者は商標の識別性によって個別の商品又は役務の出所を識別することができるのであり、商標権は商標権者の利益及び消費者の混同・誤認回避の公共の利益にかかわっており、『商標のパロディ品』を認めようとするのであれば、著名商標を模倣した商標は必ず、諧謔、風刺又は批判等の娯楽性を具備し、かつ、二つの対照的な矛盾するメッセージを同時に伝えるものでなければならず、また、『混同回避の公共の利益』と『自由な表現の公共の利益』を衡量しなければならない」、「被告は、消費者は『塗料の落ちた留め金具』のデザインを見ればそれを理解して笑うはずであり、事件で差し押さえられたハンドバッグの『塗料の落ちた留め金具』のデザインがパロディのデザインである(世界的ブランドの著名商標の塗料が落ちるわけがない)ことを明白に理解している、などと主張しているが、『諧謔の娯楽性』に該当すると認めることができるとしても、その表現しようとする、附表1に示される商標が確立したイメージと相反する又は矛盾するメッセージは何なのかについて、被告の具体的な表明は見られず、『塗料の落ちた留め金具』のデザインが表現作品との最低限の関連性を有するとは認めがたく、それが何らかの文化的貢献又は社会的価値を有するとして商標権に対する保護を犠牲にする必要性があると判断することはできず、実際にはビジネス上のフリーライド行為に該当する。
したがって、この部分についての被告の抗弁は、採用できない」というものであった (知的財産裁判所刑事判決103年度刑智上易字第63号参照)。
一方、日本では、前記の「SHI-SA」による「PUMA」模倣事件において、裁判所は、「『パロディ』なる概念は商標法の定める法概念ではなく、講学上のものであって、商標法第4条第1項第15号に該当するか否かは、あくまでも法概念である同号該当性の有無により判断すべきであるのみならず、後記のとおり、原告は引用商標C等の補助参加人の商標をパロディとする趣旨で本件商標を創作したものではないし、前記のとおり、本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないのであって、必ずしも補助参加人の商標をフリーライドするものとも、希釈化するものともいうこともできない」と判断している(日本知的財産高等裁判所の平成21年(行ケ)第10404号商標登録取消決定取消請求事件参照)。
また、前記の「フランク三浦」による「FRANCK MULLER」模倣事件において、裁判所の判断は、「本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かは、あくまで本件商標が同号所定の要件を満たすかどうかによって判断されるべきものであり、原告商品が被告商品のパロディに該当するか否かによって判断されるものではない」というものであった(日本知的財産高等裁判所平成27年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件参照)。
上記を総括すると、日台双方は原則として、いずれも商標の類似性及び混同を生ずるおそれという基準による判断に回帰している。米国の裁判所の実務で演繹により導き出された「パロディ」の概念について、日本の裁判所では、「パロディ」は学理上の概念であるとの言及にとどまっており、判決の基礎として引用しておらず、一方、台湾の知的財産裁判所では、上記の二つの事件の両方でLV事件に言及しており、さらには、「塗料の落ちた留め金具」事件では、LV事件における一部の理論(例えば、「パロディ」の要件を満たしていれば商標権は制限されるはずであるということ)を引用しているようである。もっとも、「塗料の落ちた留め金具」事件は刑事訴訟であり、上記の他の三件が行政訴訟の性質に属するのとは異なり、刑事訴訟では、裁判官が表現の自由と商標権とのバランスをより考量することから、被告が「パロディ」の論述を引用して抗弁することを受け入れる可能性が比較的高いのかもしれない。
また、日本では、有名な手土産品である「白い恋人」が、吉本興業の販売する「面白い恋人」という商品のパッケージがその商標権を侵害しているとして告訴したこともある。最終的に双方は和解したが、その和解条件は、両者の類似度を低下させるために、「白い恋人」に以前からあったリボンの装飾を「面白い恋人」から除去しなければならないというものであった。このような和解条件は、ビジネス的観点から考量したものであるかもしれない。
メディアが「面白い恋人」について報道する時、通常は「白い恋人」も共に引き合いに出されることとなり、「面白い恋人」が出てくることによって逆に「白い恋人」の知名度を上げることができ、また、両者の文言の意味には大きな違いがあるため、「白い恋人」のブランド価値、商品イメージが「面白い恋人」の存在によって容易に損なわれることはない。
この事件から分かるように、所有する商標が、模倣者が出現する程度にまで有名になった時に、模倣者がもたらし得る商業効果を考慮に入れ、利害と損得について判断した上で、どのような法的手段を用いて対処すべきかを決定したほうがよい。このような戦略的思考は、LV事件における「パロディ」についての「成功したパロディは、一つのイメージを作り上げることによって当該著名商標の識別性を高めることができるはずである」というもう一つの論述にも相通じている。
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。
執筆者紹介
国立陽明大学生命科学学部在学中、基律科技智財有限公司でのアルバイトをきっかけに、大学卒業後も同社で特許技術者として台湾における特許出願(主にバイオ分野)に関する業務に従事。2011年から政府機関の中華民国行政院原子力委員会原子力研究所に勤務。同所の主力製品である放射性医薬品、バイオ燃料等の研究開発に付随する知的財産の権利化・ライセンス業務に携わる。2012年に台湾の弁護士資格を取得後、フォルモサンブラザーズ法律事務所に入所し、研修弁護士として知的財産訴訟業務に携わった。2015年4月、公益財団法人日本台湾交流協会の奨学金試験に合格し来日、国立一橋大学国際企業戦略研究科に学ぶ。2017年3月同大学研究科を修了、同年4月に弁護士法人黒田法律事務所に入所。
